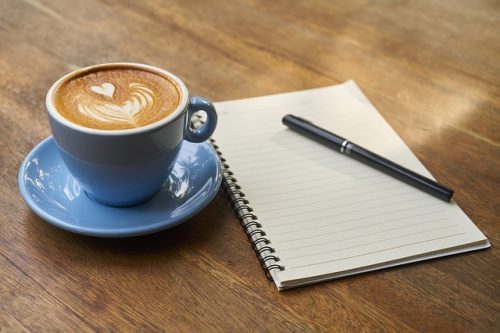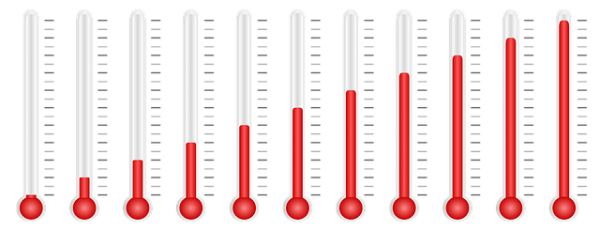お通夜やお葬式に参列するとき、お悔やみの言葉ってふと悩んでしまいますよね。
ご遺族の気持ちを考え、失礼にならないように言葉を選んで、使っていきたいものです。
今回は「ご愁傷さまです。」といったよく使われるお悔みの言葉の意味と正しい使い方と使われる場合になったときの返事などをお伝えします。
ご愁傷さまですの意味
「ご愁傷さまです」の、「愁傷」は傷を愁うと書いて「悲しみ」をあらわす意味の言葉です。
そしてご(御)とさま(様)は、敬意をあわらしますよね。
ですので「ご愁傷さまです」というのは、
ご不幸があった人に対して「お気の毒さまでございます」という意味でいった気持ちをこめて言うことばです。
近しい人の死という不幸な傷をおった相手の胸中を推し量って心配しておりますといったような意味を表すことばとして使われているのですね。
ご愁傷さまですの使い方
「ご愁傷さまです。」にもう少し言葉を加えるとしたら、どういった言葉が使い方として適しているのでしょうか。
■この度はご愁傷さまです
これは、基本によく使われます。
■ご愁傷さまでございました。
でも問題ありません。
もちろん、これだけでもいいのですが、何かほかに言葉を付け加えるとしたら、
一般的には
「気落ちなされませんように。」
「胸中お察しいたします。」
「このたびは本当に突然のことで言葉もありません。」
お世話になった人や恩師などの場合は、
「○○株式会社を代表致しましてご遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。」
ご遺族の皆様のお気持ちを思うと言葉もございません。心よりお悔やみを申し上げます。」

■受付での挨拶の場合
とお悔やみの言葉を言ったあと、香典を受付に出します。
これで十分ですが一言付け加える言葉としたなら、

ご愁傷様です以外のお悔みをあらわす言葉
「ご愁傷様です。」は、通夜や葬儀で使われる、基本的なお悔やみの言葉です。
しかし、なにかかしこまりすぎてというか、言い慣れないため、使いにくい方も多いです。
また、「ご愁傷さま~。」と普段に使う場合は、ちょっと小ばかにした意味でつかわれることもある言葉です。
そんなとき「ご愁傷さまです。」の代わりに使かうお悔みのことばとすれば、
「お悔やみ申し上げます。」
がいいのではないでしょうか。
「ご愁傷様です。」と同じ様に、「この度は、お悔み申し上げます。」といった感じで使うといいですね。
また、身近な近しい人だったりしてもっとかしこまらない言い方としたら
「たいへんでございましたね。」
「たいへんでしたね。」
といった平易な言い方でも十分です。
「この度は突然の事でお寂しくなられましたね。何かあったら遠慮
なく言って下さいね」
などといった言葉も相手に対しても気遣いがとても伝わる言葉ですね。
相手のつらい心中を察っしてのおもいやりが伝われば、ご自身の言葉でいいのではないでしょうか。
ご愁傷様ですの返事は?
それでは、今度は逆に自分が「ご愁傷さまです」などのお悔やみを受ける立場になったときのことですが、
相手がお悔みの言葉を用いた挨拶をしてくださったことに対し、どう返事をしたらいいのでしょうか?
基本は、
「恐れ入ります。」
「お心遣いありがとうございます。」
でいいと思います。
または、「ありがとうございます。」でもいいです。
ただ、弔問をしてくださった相手のかたの状況により、
「遠方のところ、ご足労いただきましてありがとうございます。」
「お忙しい中お越しいただきまして、ありがとうございます。」
など葬儀や通夜に参列してくださった方に対しての感謝の気持ちをそえて伝えてもいいと思いますね。
ま と め
喪主が近しい友人や気の置けない間柄だとしても、基本的に気を付けるべきことはあります。
また、取引先の方やお仕事関係、お世話になった目上の方の関係だとしたらしっかり相手を思いやるお悔みの挨拶をしたいものです。