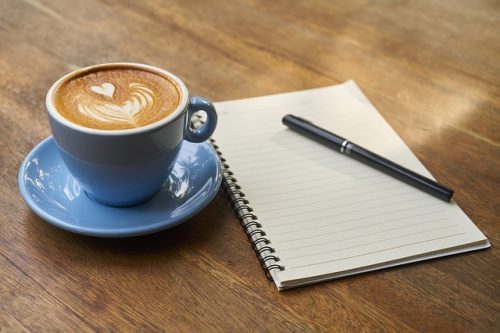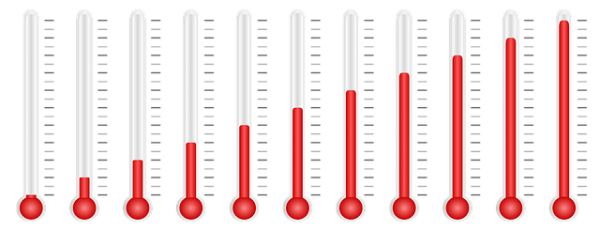歌舞伎と言えば男性の世界だと思っている方は多いですよね。
当たり前に思っていたのですが、外国人の方などにすれば、なんで女性が歌舞伎にでていないのか不思議に思うこともおおいようですね。
では、何故女性が歌舞伎役者になれないのか?
女性禁止といった理由があるのか?
そして、女性であっても子供のであれば歌舞伎の舞台にたつこともあるようですがいつまで舞台にたてるのかなどなど歌舞伎の歴史を簡単にお伝えするとともに疑問について考えていきます。

歌舞伎の歴史を簡単に!
■歌舞伎の始まりは女性の踊り
歌舞伎の歴史は、出雲の阿国の「かぶき踊り」からはじまったといわれています。
この「出雲の阿国」は女性です。
阿国が活躍するのは戦国時代、
1603年「当代記(とうだいき)」という史料に
「この頃、かぶき踊りというものが踊られた。出雲の巫女(みこ)を名乗る国という女性が、京に上り変わった風体の男の扮装をして踊った」
という意味の記述が残っています。
史料にある「変わった風体の男」とは、
当時流行していた、奇抜な服装をし、世間の秩序に反して行動する「かぶき者」とよばれた人々です。
「かぶき」は「傾く(かぶく)」という動詞から派生した言葉です。
阿国の踊りは、
かぶき者の扮装をまねた男姿で、茶屋で遊ぶ様子などを演じたため
「かぶき踊り」とよばれました。
この「かぶき踊りは」大人気を得ていきます。
歌舞伎の歴史は、女性の踊りからはじまったのですね。
■出雲の阿国
この「国」という女性が「出雲の阿国」だといわれています。
阿国は、現在の島根県である出雲の国の出身です。
1572年に誕生したといわれています。
出雲の国の出雲大社の巫女として幼いころから全国各地を興行しながらお金を稼ぎ、出雲大社の修繕費用や出雲の国の為の出稼ぎといったようなことをしていました。
そういった女性は阿国の他にももちろんいるのですが、阿国の踊りの才能や興業の才覚は別格でした。
1582年阿国が10歳のときには奈良の春日大社で披露した「ややこ踊り」が話題となります。
その後、京都の北野天満宮境内での興行で人気をはくし当時の皇室の女性に庇護されたり、公家や秀吉などにも披露したりするようにまでなります。
その「ややこ踊り」をしていた阿国が成長するにしたがって興行の成功を模索するうちに「かぶき踊り」といった形態にかわっていったと思われます。
■女歌舞伎は若衆歌舞伎~野郎歌舞伎
このように阿国創始者といわれる「かぶいた男」を表現する男装の踊り「女歌舞伎」はかなり人気になったため他の遊女や女の芸人の一座も次々にマネた興行を行います。
そして、京都だけでなく他の地方や江戸などにも広がっていきました。
遊女など興行を行うといったことからもわかるように「女歌舞伎」はたんなる興行といったものではなく、遊女の商売にもつながるようなシステムをとることもしていたようです。
そういったこともあり風俗を乱すといった理由で1629年頃から「女歌舞伎」禁止令がでました。
その後、「女歌舞伎」に代わって人気になったのが
前髪のある成人前の少年が演じる「若衆歌舞伎(わかしゅかぶき)」です。
しかし、こちらも風俗的要素があり、風俗を乱すといった同じ理由で
1652年頃から禁令が出されるようになりました。
その後、前髪をそり落とした野郎頭(やろうあたま)の成人男性が演じる
「野郎歌舞伎(やろうかぶき)」に変わっていきます。
■野郎歌舞伎が発展
そういった幕府による禁止令などの流れがあり、成人男性が演じる「野郎歌舞伎」が中心になっていくわけですが、そのなかでそれまで容色が重要視されていた舞台がより技術的、ストーリー性をもつものに変化していきます。
それまで「若衆歌舞伎(わかしゅかぶき)」の時代にも、女性役を演じる「女方(おんながた)」は存在しました。
そうした「女方」も野郎歌舞伎では、専門に演じる俳優が登場してきます。
また、はじめは歌や踊りによる短い場面で完結した「離れ狂言(はなれきょうげん)」をいくつか続けて上演するスタイルであったものも次第にストーリー性をもつ複数の場面からなる「続き狂言(つづききょうげん)」が上演されるようになります。
そうした複雑化したストーリーを的確に表現するために、登場人物を類型化して演じるようになってきます。
このようなことからできた型は
若い女性を演じる「若女方(わかおんながた)」、
男性役の「立役(たちやく)」、
男性の悪人の「敵役(かたきやく)」、
中年から老人の女性を演じる「花車方(かしゃがた)」、
滑稽な役を演じる「道化方(どうけがた)」
などがあります。
こうしてそれぞれの役柄にあった演技術が編み出され、
役の年齢や性格に基づいた「役柄(やくがら)」が確立されてきました。
■江戸の荒事
1688年頃以降は、野郎歌舞伎(やろうかぶき)ではない歌舞伎が江戸と上方でそれぞれで大きく発展していきます。
江戸では、「荒事(あらごと)」を得意とした初代市川團十郎(いちかわだんじゅうろう)が活躍していくことになります。
「荒事」とは、
「見得(みえ)」や「六方(ろっぽう)」などの演技や、
「隈取(くまどり)」をはじめとする扮装によって
表現される豪快で力強い芸のことです。

歌舞伎に女性が出られない理由は?
何故、歌舞伎は女性は舞台に立つことができないのでしょうか?
歌舞伎の歴史をみてきても当初は「女歌舞伎」の禁止令があったとはいえ「禁止」されているといったことではありません。
大相撲等も土俵には女性は上がれないといったものがありますが、歌舞伎はそういった神聖な舞台であるといった理由から舞台に上がれないといったことではありません。
歌舞伎役者に女性がいない理由は
「歌舞伎の芝居には女優が合わない」
からだといえます。
歌舞伎の歴史をみてもわかるように
女性の歌舞伎からはじまった歌舞伎は江戸時代にリアルな容色から
成人男性が演じる登場人物を類型化して演じるような型によって成り立つ
ように転じてきた
「倒錯の世界」です。
発声や、衣装や、舞台演出も型があり、
女形と立役(男役)といった世界観が確立されています。
そこにリアルの女性が入ると現実に引き戻された感がでてき違和感がでてしまいますね。
また、女形がある歌舞伎では、女形の男性に比べるとどうしても骨格も小さい
女性が立つと、全体のバランスもとれないですね。
そういった理由で女性が歌舞伎の舞台にたつといったことはないのでしょう。
また、女性が舞台に立つということが絶対的な禁止事項でないということですから、
東京都武蔵野市吉祥寺に拠点を持つ「前進座」の歌舞伎には女優も出ることがあります。
前進座は、昭和6年に松竹の歌舞伎から分離した歌舞伎劇団になります。
そして、
子役なら女子がたくさん出ています。
音曲でも一中節が使われるときは舞台上座に並ばれます。
黒御簾と呼ばれる下手の鳴物は女性が担当されることも多いです。
そのように歌舞伎に絶対的に女性を排除しているといったことではなさそうです。
しかし、国立劇場の歌舞伎は文化財ですので、女優の出演は禁止になっています。
女の子はいつまで歌舞伎の舞台に出られるの?
このように子役や音楽なら女も舞台に立てると言われる歌舞伎の舞台です。
かつては、女優の松たか子さんも父の松本幸四郎さん共演したこともあるそうですね。
子役として歌舞伎の舞台にはいくつまで立つことができるのでしょうか。
何歳といった明確なものはないと思いますが、子役ということで10歳ぐらい
女の子といった風情であるといったことは必要なのではないでしょうか。
そして、歌舞伎の舞台の子役としては、
歌舞伎の家系の子女ではなくても一般のお子様でも舞台に出演することはできるようですよ。
ま と め
歌舞伎役者に女性いない理由や舞台に上がるのは禁止なのかといったことや女の子は舞台にいくつまで上がれるのかなどについて調べてみました。
歌舞伎に女性が出ない理由は、歌舞伎の歴史から成人の男性の演じ分ける型によって完成している虚構の世界観に女優があわないといった理由からでした。
逆に宝塚の舞台にいくら美男子であるからといって男性俳優がでると世界観は変わってしまうことから考えてもそういうものだなと思います。
また、女の子供も10歳くらいまでは歌舞伎の舞台にたつこともあるそうです。
歌舞伎は歴史がある、日本固有の伝統芸能の一つです。
重要無形文化財であり、ユネスコ無形文化遺産の代表一覧にも記載されています。
歴史をみることによって独特の世界が出来上がった背景もわかりさらに歌舞伎をたのしめそうですね。
歌舞伎を継承する勸玄くんの挑戦する宙乗りについてはコチラ
↓
歌舞伎の宙乗りと宙返りとは?勸玄くん7月大歌舞伎で最年少披露!
歌舞伎の初お目見えと初舞台の違いはコチラ
↓
初お目見えと初舞台の歌舞伎で意味の違いや年齢!子息のデビュー一覧