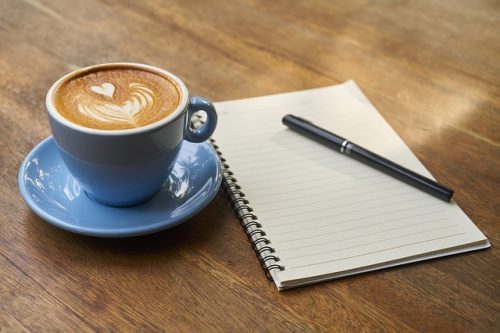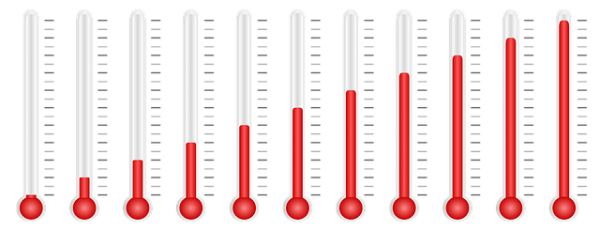お祝いやお見舞い、挨拶、弔慰など毎日の生活の中で、熨斗紙や熨斗袋などを使う機会は思ったよりも多いのではないでしょうか?
そのときに必要な熨斗(のし)の表書きです。
熨斗(のし)表書きの種類一覧!書き方と意味やマナーとお礼には?なにがいいのかをお伝えします。
熨斗(のし)表書きの書き方とマナー
熨斗(のし)をつけるといったことをを面倒がる人もいますが、やはり単になにも書かれていない真っ白な封筒にボンとお金などを入れて渡されると考えるとやっぱり、なんともいえず味気ないものですね。
最近では、コンビニエンスストアなどでも熨斗袋も表書きが印刷されたものが用意されています。
そので見かけるのは「御祝」、「寿」、「御見舞い」などある程度想定される場面で使われるものです。
ですが、熨斗の表書きの種類はもっとたくさんあります。
もし、できるのならばそのっ細やかな状況に応じたふさわしい表書きを書きたいものですね。
表書きの書き方ですが、書く位置は水引よりも上のスペースでほど真ん中あたりです。
大きな文字で字と字との間隔のその文字数を考えて適度にあけてかきましょう。
自身の名前は、水引の下側のスペースにちょうど真ん中かやや左寄りに表書きよりも小さな文字で書くのがマナーです。
金額とこちらの住所は、中袋か上包みの裏側にかきます。
特に弔辞の場合は重ねることを嫌うといった意味から上包みだけとなりますから、裏側に書くことになります。
金額の数字は、横書きではない場合は、縦の漢数字を使うのが正式な書き方になります。

熨斗(のし)表書きの種類と意味一覧!
■お祝いの表書き(子供関係等)
| お祝い | 初宮参りのお祝いなどに |
| 御初穂料 | 初宮参り、交通安全祈願、厄除祈願、安産祈願、初宮詣、七五三詣など神社で執り行うすべての祭事で神社へのお礼に |
| 初節句御祝 | 桃の節句、端午の節句などの初節句のお祝いに |
| 初雛御祝 | 女の子の初節句のお祝いに |
| 初幟御祝 | 男の子の初節句のお祝いに |
| 祝初誕生日 | 初めて迎える誕生日に |
| 七五三御祝 | 三歳、五歳、七歳のいずれにも使える表書き |
| 賀御髪置 | 三歳の時のお祝い。三歳の時に髪をもばす「髪置」の習慣から由来する表書き |
| 袴着祝 | 五歳の時のお祝い。五歳の男の子のお祝い時に初めて袴をつける「袴着」が由来する表書き |
| 賀御帯解 | 七歳の時のお祝い。七歳の女の子のお祝い時に初めて本式の帯をしめる「帯解」が由来する表書き |
| 十三祝い | 十三歳のになったことを祝う十三祝いの表書き |
| 祝御成人 | 成人式あるいは満二十歳の誕生日のお祝いの表書き |
| 賀成人式 | 成人式を祝う表書き |
| 御香料 | 心身の健康の祈願等お寺にお世話になったとの謝礼のときに |
■結納・結婚式等のお祝いの表書き
| 御結納金 | 金包みの名称 |
| 御帯料 | 男性から女性に贈る金包 |
| 御袴料 | 女性から男性に贈る金包 |
| 寿 | 結婚祝いによく使われる。祝い事の中でもっとも格式の高い表書き |
| 御祝 | 挙式前のお祝いに使う。お金以外の品物を贈るときにも応用できる。 |
| 祝御結婚 | 結婚祝に使う。四文字が気になるのなら「祝」の字を大きくする、話して書くなどの工夫を |
| 御結婚御祝 | 「寿」とともによく使われる表書き |
| 酒多留料 | 結婚祝いに一般的に使われる |
| 御酒肴料 | 仲人にもてなしに代わって御礼と別に渡すお金。 |
| 御礼 | 仲人へのお礼「寿」 |
| 内祝 | 披露宴に招待できなかったのにお祝いをくれた人に |
| 寸志 | 仲人へのお礼に。上品な表書き、「こころ」とも書く |
| 粗品 | お祝いのお返しに |
| 御祝儀 | 挙式でお世話になった手伝いの人や運転手、美容師などへのお礼に |
| 御車代 | 結納のとき仲人の自宅と違った場所で行ったときに渡すお金 |
| 御土産 | 新婚旅行のおみやげの品に |
■結婚記念や受賞を祝う表書き
| 祝結婚記念日 | 結婚記念日のお祝いに |
| 祝紙婚式 | 結婚一周年のお祝いに |
| 祝銀婚式 | 結婚二十五周年を祝って |
| 祝金婚式 | 結婚五十周年を祝って |
| お祝い | 入選入賞した人を祝うときに |
| 祝受賞 | 展覧会、コンクールなどで選ばれた時に |
| 祝入選 | コンテストやコンクールなどで入選したときに |
| 寿 | 受賞祝いを頂いたときのお返しに |
■長寿(敬老)を祝う表書き
| 寿福 | 敬老の日や長寿のお祝いに |
| 賀華甲 | 還暦祝い。華は十が六つ、一が一つからなり六十一歳をさすための表書き。 |
| 祝古希 | 七十歳の誕生日に |
| 祝喜寿 | 喜の草書体が七十七に似ているところから七十七歳の誕生日に |
| 祝米寿 | 米の字が八十八に似ているところから八十八歳の誕生日に |
| 祝白寿 | 百から一をとると白になるところから九十九歳の誕生日に |
| 御上寿御礼 | 九十歳、百歳、百二十歳のお祝いに |
| 祝延寿 | 敬老の日や誕生日に長寿を祝うときに |
■懐妊や出産を祝う表書き
| 御帯祝 | 金品を帯祝に贈るときに |
| 岩田帯 | 祝い帯にもつかうが、神社や子宝に恵まれた人から贈られることもある |
| 御帯 | 仲人が妊婦に、また他人が知り合いの妊婦に帯祝に贈るときに |
| 帯祝い | 妊婦の両親が娘に腹帯を贈るときに |
| 寿 | 妊婦の実家から娘に腹帯を贈るときに |
| 酒肴料 | 両親から妊婦の娘に腹帯を贈るとともにお金を贈るときに |
| 御玉串料 | 安産の祈願を神社でしてもらったときのお礼 |
| 御帯内祝 | 帯祝いのお返しとして |
| 御出産祝 | 産後三週間以内に金品を贈って祝うときに「祝御出産」 |
| 御初孫御祝 | 孫が初めてでき、おじいさんおばあさんになる人に |
| 御初着 | 赤ちゃんに初めて着せる衣類を妻の実家から贈るときに |
| はだぎ料 | 子供用の衣類の代わりに産婦の実家からお金を贈るときに |
| 内祝 | 出産通知をした人に配る品に。お宮参りの頃に届ける「出産内祝」 |
| 祝命名 | 赤ちゃんに名前がついたことを祝って両親に金品を贈るときに |
| 命名御礼 | 名付け親が身内以外の人の場合、お礼の品に |
| 御膳料 | 出産でお世話になった人に祝宴代代わりの御礼としてお金を包むときに |
■入学・卒業・就職を祝う表書き
| 御祝 | 入学や卒業のとき、身内でお祝い金を贈るときに |
| おめでとう | 本人に手渡すときに |
| 祝御入園 | 幼稚園、保育園の入園を祝ってお祝いを贈るときに |
| ご入園おめでとう | 本人に手渡すときに |
| 祝御入学 | 入学祝いに |
| 御入学祝 | 身内が入学を祝って金品を贈るときに |
| にゅうがくいわい | 本人に手渡すときに |
| 合格御祝 | 入学試験に受かった時に |
| 御進学祝 | 中学高校大学と進学を祝うときに |
| 祝御留学 | 海外留学のお祝いに |
| 祝御卒業 | 最終学校の卒業を祝って |
| ご卒業おめでとうございます | 卒業のお祝いに |
| 御服地料 | 社会人の門出にスーツでもご新調くださいといった気持ちを込めて |
| 賀社会人 | 社会人へ巣立つお祝いに |
| 祝御就職 | 就職を祝うと行に。再就職の人なら初出勤のお祝いに |
| 就職おめでとうございます | ごく親しい人の身内の最終学歴の卒業、就職のお祝いに |
■葬儀の表書き
| 御仏前 | 四十九日の法要がすんでからの香典に |
| 御霊前 | 神葬祭にも使うが一般的に通夜、葬儀の香典に |
| 御香料 | 霊前や仏前に香や花を供える代わりにお金を供えるときに |
| 御弔典 | 会社などからその社員や職員の関係する葬儀に香典をおくるときに |
| 御悔 | 身内や親戚以外の故人の知人が遺族を見舞ってお供えするとき |
| 御線香料 | 線香を霊前から絶やさないようにという意味のお金 |
| 菊一輪 | 少しのお金を供えるときに。奥ゆかしい表書き |
| 御供 | 葬式や法要の時にお供えするもの |
| 御玉串料 | 焼香でなくた玉串奉奠をする、神式の葬儀の香典 |
| 御榊料 | 「榊」は神木。神式葬儀の香典の表書き |
| 御神饌料 | 神式葬儀の香典の表書き。「神饌」は神に供える清く新鮮な酒食 |
| 御神前 | 神式葬儀の香典の表書き。 |
| 献金 | キリスト教式の葬儀で教会へのお礼に。白封筒を使う。 |
| 御花料 | キリスト教式の葬儀では香典の代わりに献花をする |
| 御ミサ料 | 香典にあたる。主にカトリック教会で |
| 御白花料 | キリスト教式の香典にあたる、棺を白い花で飾り死者を送ることから由来する |
■香典返しの表書き
| 志 | 仏式の葬式の香典返しの品に |
| 忌明 | 「志」の丁寧な書き方 |
| 偲び草 | 神式の香典返しのこと。五十日祭の後に贈る |
| 満中陰 | 関西地方でよく使われる香典返し |
| 御会葬御礼 | 葬式や、告別式の日に参列者に配る令状「一礼」 |
| ご挨拶 | 香典や弔電、供物、花輪などを頂いたときの礼状に |
■法要の表書き
| 御香資 | お香の代わりに持参する法要に招待された時のお金に |
| 御霊前 | 仏式にかかわらず使える最もポピュラーな香典の表書き |
| 御仏前 | 年忌法要によく使われる |
| 御神前 | 神式の霊前の時の香典に |
| 御花料 | キリスト教の記念、追悼ミサのときに |
| 粗供養 | 法要の出席者にお礼や記念に渡す引き出物の表書き |
| 茶の子 | わずかばかりの気持ちという意味。「粗供養」と同じ |
| お布施 | 寺や僧侶への仏事のお礼に |
■御見舞いの表書き
| 御見舞 | お見舞いの金品によく使われる「御伺い」 |
| 祈御全快 | 一日も早い全快を祈る気持ちも込めて |
| くだもの | お金か果物を持っていくときに |
| 快気祝い | 退院や床上げをしたときにお見舞いをしてくれた人へのお返しに |
| 快気内祝 | 「快気祝い」と同様の意味で、家の内での祝いごとの意味 |
| 本復祝 | 「快気祝」のやや古風な言い回しの表書き、「本復内祝」 |
| 謝御見舞 | 感謝が強い時のお礼に |
| こころ | お見舞いに来てくれた人に感謝の意をあらわす |
| 災害御見舞 | 天災に遭った人へのお見舞いに |
| 出火御見舞 | 火事に遭った人へのお見舞いに |
| 水害御見舞 | 集中豪雨や洪水などの水害に遭った人へのお見舞いに |
| 陣中御見舞 | 楽屋や催事の詰め所、選挙事務所や合宿などに持参する金品に |
| 祈御健闘御 | 選挙事務所や合宿など御見舞いとして持参する金品に |
| 楽屋御見舞 | 発表会などの楽屋に励まし金品を持っていくときに |
| 御盛会御祝 | 何かの会に招かれた時に渡すお祝いの金品に |
| 御勝手御見舞 | 懐石料理などの解釈に招待された際に、材料費の一部として渡すお金 |
■昇進・栄転・開店の表書き
| 祝御昇進 | 昇進した人へのお祝いに。「御昇進御祝」 |
| 祝御栄転 | 栄転する人へのお祝いに「御栄転御祝」 |
| 御引退記念 | 定年退職者への記念品に「記念品」 |
| 御勇退記念 | 自分の意思で退職する人にへの金品を贈るときの表書き。 |
| 祝御開店 | 店のオープンを祝って送る金品に。 |
| 祝御開業 | 医院や事務所を開いた人へのお祝いに |
| 御創業御礼 | 事業や事務所の開業のときに |
| 花輪代 | 花輪代わりに現金を贈るときに |
■新築の表書き
| 御神饌料 | 上棟式や地鎮祭などの祭祀料に |
| お車代 | 神職を遠方から呼んだ時に包むお金 |
| 御祝儀 | 施主が上棟式に現場関係者に祝儀などを渡す時に。「酒肴料」 |
| 御新築祝 | 増改築のときも使えるが一般的には新築した人へのお祝い |
| 祝御新居 | マンションや新居を購入したなど新居に入った人へのお祝いに |
| 御改築御礼 | 家の一部を改築したお祝いに |
| 祝御竣工 | ビルなど大きな建物の完成祝いに「祝御落成」 |
| 新築内祝 | 新築のお祝い返しに |
■季節の挨拶・中元・お歳暮の表書き
| 御年賀 | 年始まわりの品に「御年始」「御勝栗料」 |
| 賀正 | 「御年賀」と同じく年始まわりの品に |
| お年玉 | 目下の人や子供にあげるお年玉に |
| 寒中お見舞い | 立春まで使う。松の内に年始回りができなかった場合に |
| 御中元 | 関東では7月上旬から8月中旬。関西以西では、7月中旬から8月中旬。 |
| 暑中お見舞い | 立秋まで使う表書き、お中元の時期を過ぎてから贈る品に |
| 残暑お見舞い | 立秋から9月中旬までに使う表書き、お中元やお返しが贈れたときに贈る品に |
| お歳暮 | 暮れの挨拶の品に |
■謝礼の表書き
| 謝礼 | 講師、指導、発表などに参加依頼をしたときに |
| 講演料 | 講演のお礼に。「講演御礼」 |
| 執筆料 | 雑誌や書籍、広報、社内報などに原稿を書いてもらった時に |
| 原稿料 | 雑誌やイラストレーションなどを書いてもらった時に |
| 揮染料 | 「揮染」は神を色で染めること。絵をかいてもらったお礼に |
| 揮毫料 | 「揮毫」は筆をふるうこと。書画をかいてもらったお礼に |
| 命名料 | こどもの名前を専門家などにつけてもらったお札に |
| 見積料 | 見積作成の代金に |
■日常での贈り物の表書き
| 拝呈 | 目の上に物を贈るときに |
| 謹呈 | 目上の人に謹んで物をさしあげるという気持ちを伝えるときに |
| 進呈 | 同輩や目下の人にものを贈るときの丁寧な言い回し |
| 贈呈 | 「進呈」よりやや格が下がる。団体や会社などにものを贈るときに |
| 謹謝 | 目上の人などにあらたまったお礼の金品を贈るときに |
| 薄謝 | 仲人や講師へのお礼、また目下へのお礼やお返しに |
| 感謝 | 父御日、母の日など何かのお礼のときに |
| 上 | 「さしあげます」という意味であらゆる贈り物に使える |
| 寄贈 | 団体、学校、会社に金品を寄付するときに |
| 御祝儀 | 祝宴やお祭り引っ越しなどに手伝いをしてくれた人や世話人へ |
| お礼 | 人へのお礼をするときにする表書き |
| おみやげ | 女性からの贈り物に使うとやさしい印象になる表書き |
| 寸志 | 目上の人には決して使いません。目下の人に手伝いを頼んだ時に |
| 松の葉 | 松の葉にかくれるほどかずかなという意味の表書きです。「みどり」 |
| 御挨拶 | 引っ越し先でのあいさつまわりや人に何かを依頼するときに |
このように様々なシーンでの表書きがあります。
お祝いやお見舞い、挨拶、弔慰など毎日の生活の中で、熨斗紙や熨斗袋などを使う機会は思ったよりも多いのがわかります。
こういった細やかな内容にそった表書きを印刷でなく自身で書くと同じ贈るにしてもグッとこころがこもったものになります。
熨斗(のし)表書きの種類一覧をご参考にそれ以外にもそれぞれの目的にそった表書きを書くようにすると気持ちが伝わり印象に残ると思いますね。